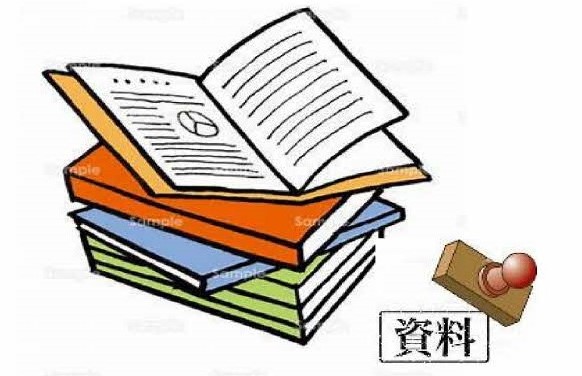松河戸関連資料
(1) 地域誌(古文書) 松河戸関係分
| 書名 | 内 容 | 松河戸関係分 | リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 麒麟抄 |
全八巻から構成されており、書法や書論の秘伝が集約されている。 著者は不明で平安時代の書道家である藤原行成や空海が著したという説が有力視されていたため 日本における現存最古の書論書とも言われていたが、近年の研究では否定されている。 |
麒麟抄の書き写し 国立国会図書館 大正3年復刻版 道風公出生の記述は 33/50 6巻P44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 塩尻 | 江戸中期の随筆。天野信景(あまのさだかげ)(1663―1733)著 元禄10年(1697)ごろから享保18年(1733)に執筆され、原本は1000巻に及ぶともいう。 著者は尾張藩士で、博学の国学者として知られ、その合理主義的な学風は、吉見、幸和 ら当代の尾張の学者や文人はもちろん、平田篤(あつ)胤(たね)らにも大きく影響した。 本書は、有職(ゆうそく)故実(こじつ)を中心に広範囲な分野にわたる和漢の典籍や自己の見聞を抄録 してある。 |
明治40年抄録出版の一部 国立国会図書館 道風の出生の記述は冒頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ 張州府志 | 宝暦2年(1752) 尾張徳川家8代徳川宗勝は、学者の松平君山と千村伯斎を責任者として尾張全域を 調査し全30巻・付図1巻の「張州府志」を完成させた。 これが官選地誌の第1号といえる。漢文で格調高く書かれている。 |
張州府誌の書き写し 名古屋市 大正3年第10巻から第13巻 (11巻から13巻春日井郡) 道風公出生の記述は 31/76 11巻P53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張州府誌の書き写し 国会図書館 春日井郡 松河戸 37/57 小野道風 44/57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ 張州雑志 | 尾張徳川家9代藩主・徳川宗睦の内命を受けて、正参が安永年間頃(1772年 - 1780年)から領内を 調査して執筆したもの。 正参は狩野派の絵師として東甫の名で知られており、内容には多くの絵も含まれる。 正参が天明8年(1788)に没したため、協力していた赤林信定によって残された原稿などを元に 全百巻本として編纂され、寛政元年(1789)に宗睦へと献上された。 広く公開されることはなく明治を迎え、その後は名古屋市蓬左文庫へと引き継がれている。 (尾張の内容が細密に記録されていたことにより「御秘本」扱いになったと考えられる) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤尾張志 | 天保15年(1844)に藩命によって編纂された尾張国の地誌。 宝暦2年(1752)に完成した尾張藩最初の藩撰地誌『張州府志』をもとに、再調査を行って改撰、 和文で著された。 名古屋城下、熱田、各郡別に、境域沿革、郷村、人物、物産、神社、寺院、名所、旧跡などを挙げる。 藩校明倫堂の督学をつとめ、当時書物奉行であった深田正韶が監修し、尾張藩士岡田啓、中尾義稲ら が執筆、付図を小田切春江が担当した。
|
原本は蓬左文庫に所蔵されており、序巻を含めて全61巻、付図が14枚ある。 尾張志の書き写し 春日井郡抜粋 愛知県図書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥寛文村々覚書39村 | 尾張藩では明暦年間(1655~1658年)に村勢調査を着手したが、一部『美濃国尾州村々覚』 が現存 するのみで全容は解らず、寛文年間(1670年前後)に編纂され現存する同書が尾張藩 一円の村勢を知る 重要な書であり現在でいう国勢調査書の体をなす。 また近世初頭の尾張 藩の歴史を知る上でも同書は重要な位置を占めている。 原本は尾張藩各郡別に『○○郡覚書帳』として作成されており、通常それらをまとめ 『寛文村々覚書』と言われ、守山区分は春日井郡の部にまとめられている。 その他同地方の郷土史を知る上で重要な地誌として、尾張藩士樋口好古が著した『尾張徇行記』 があるが、石高などは『寛文村々覚書』元としている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦尾張徇行記 (尾州徇行記) |
樋口(ひぐち)好古(こうこ)が藩の官吏として藩の管轄地を巡行し、また資料を渉猟して、 著文政5年(1822年)まとめた『郡村徇行記』 樋口好古は尾張藩に仕えた農政家であったが、彼が尾張国内や美濃国・近江国の尾張藩領などを 巡検した際の記録で、村の沿革や隣村との境界、人口、租税額、寺社の除税地、河川・水路・橋梁 などを、寛政4年(1792年)春から文政5年(1822年)5月まで、31年に渡って記した。 |
尾張徇行記 愛知県図書館 第4巻春日井郡抜粋 松河戸村記述部分 NO33 137/234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧尾張名所図会 | 尾張藩士で学者の岡田文園と、春日井郡枇杷島にあって枇杷島橋の橋守役を務めていた野口市 兵衛家の8代目・野口梅居とが著し、尾張藩士で画家の小田切春江や春江の師に当たる森高雅が挿絵 を描いたもので、尾張国八郡の名所が描かれた。 全13巻。 天保9年(1838年)から天保12年まで約3年をかけて執筆され、天保15年(1844年) 2月に前編7巻が刊行された 。 |
愛知県図書館 後編4巻 道風公出生の記述は 9/66~11/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨張国地名考 (尾張地名考) |
江戸時代、尾張国海東郡(現・愛西市)の学者・津田正生 によって著された尾張国の地名について の地誌 尾張地名考の書き写し 文化2年(1807)随筆を始め、文化13年(1816)完成する。 |
国立国会図書館 大正3年復刻版 春日井郡部分抜粋 松河戸村の地名・道風の記述15/44 6巻 p155 |
(2) 関係資料 機関リンク
| 書名 | 内容 | リンク |
|---|---|---|
| 東春日井郡地誌 | 大正12年出版 地域別に地形・史跡・名所・産物などの上方が記載された資料 国立図書館 | |
| 東春日井郡地誌略 | 国立図書館 | |
| 貴重和本デジタルライブラリー | 愛知県図書館 (aichi-pref-library.jp ) |